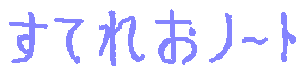 ステレオ写真日記 夜の写真 しばらく前から夜の散歩が多くなっていた。それにつれて昼より夜に撮る写真の方が増えていた。 夜の方が目が疲れず、街の喧騒もなくて静かでもあり、空気もいい、ということもあるのだが、それだけではない理由がもっと他にもあるような気がしていた。 手元にある「イメージ辞典」によれば、日本では古来、夜と昼は不連続であり、合わせて1日ではない空間的に別のものと考えられていた。(だから「蘇り」とは「夜見」の国から空間的に移動して 「帰ってくる」ことであった。) 昼と夜は生と死のように異質なものであった。 西洋ではアーリア文明の昔から、Night は宇宙生成前の暗黒、混沌、死を表象した。 −− 「魂の闇夜の時刻はいつも午前三時」(フィッツジェラルド) ( 本来なら日本やその他の古典をあれこれと研究してこのような知見を述べるべきで、いつものようにすぐ辞典に頼ってしまうのは我ながら恥ずかしいのだが、ともかく辞典はそのためにあるのだろうし、その道の専門家の研究の結果なのだろうから、謹んで利用させていただいている。) なるほど、我々の意識の奥にはそのような表象が潜在しているらしい。 夜の写真を好んで撮るというのは、そのような世界を窺おうという無意識の欲求といえるだろうか。 たしかにこれは私の生活実感と相応している。夜の東京の写真はとても「美しい風景」といえるものではない。鮮やかな色はなく、形や姿はみなおぼろげで、ものみなすべてが暗闇にとけこんでいる。しかし何か捉えがたい正体不明のものに魅せられるのを感じる。 私が見つめているのはおそらく自分の生と死との境界である。 それだけでなく、この世界の滅びとその彼方にあるものである−− すでに環境問題、人口問題は人間の制御を超えてしまったのではないか、という実感がある。 我々はいま黙示録の世界にいるのではないか。 私には「空」につづいて「夜」というテーマが与えられたと感じている。 最初の一枚 古いアルバムを見ていると一枚の写真が見つかった。それは「空」を見つめて撮った写真である。その一枚は私の写真のはじまりだった。 その写真が何であるか、見つけた瞬間すぐに分かった。そしてそれを撮った時のことが昨日のことのように思い出されてきた。それはある秋の日の昼、皇居前広場を歩いているときだった。そのしばらく前母を亡くしていた。大都会の平原ともいえるこの広場、その上に広がる広い空、まばゆい程の明るい日差しは、どういうわけかその時の私に何かを語りかけるような気がして、思わず持っていたオリンパスの小さなXAで何の変哲もないその景色を撮ったのだった。 このときから私は何かに引きこまれるようにして写真を撮るようになった。以来撮るものは色々と代わったが、この最初の写真と同じく中心には (時には周辺には) いつも「空」があったことにいま気がつく。特に意識したことはないのだが、目は自然に空に引き寄せられていた。 その後まもなく半年くらいかかって丹沢の写真を撮ったのだが、撮れているのは撮ろうとした山ではなく、実は空だったことを後になって発見した。 空を撮ろうと思って撮ったのは東北にいた頃で、まる1年間文字通り毎日空ばかり見つめていた。東北の空は本当に美しく忘れがたい。都会に戻ったいまはその片鱗しか窺うことができない。なにか大切なものを忘れてきたような気がしている。 ステレオ写真を始めたのは丹沢の写真を撮った頃からだ。撮り始めた頃の写真が見つかったが、これはどうやら秦野の小さな山の山腹で一休みしたとき撮ったもののようだ。何の変哲もないこの写真もやはり空を向いて撮っている。 空はステレオ写真では撮りにくい。でも古い写真を見返してみると、これまでに、そしていまも、執拗なまでに多くの空を撮っている。 人の写真のテーマとはどんな風にして決まるものだろうか? 私の場合そのきっかけはこのように偶然であり無意識的だった。空がいわば与えられたテーマであると実感したいまも、なぜ空なのかはよく分からない。いずれそのうちにもっとよく考えてみようと思っている。 夜の東京、昼の東京 最近夜の散歩が多くなった。何となく落ち着くのである。夜、昼とはまったく違った風景が現れる。 何とかこの夜の風景を写真に撮ってみようと思う。デジタルのステレオカメラはまだ持っていないので、当面フィルムカメラを使うことになるが、カラーではどんなに長時間露出しても色変わりのため無理だろう。使えるのは白黒だけだ。 一方、昼の街は好きでない。東京には自然がまったくない。周囲すべてが埃っぽく、どちらを向いても大きなぎらぎら輝くビルは視界を圧倒する。絶えるこのとのない人の波は息をつまらせる。そこにいるだけで疲れる。 写真に取りたい風景はここにはない。 道具の写真
コレクションの写真集は多い。○○民俗資料館の目録、○○図鑑、世界のSL図鑑、カメラ150年史、ドイツカメラの精髄、特選○○逸品シリーズ、写真で見る○○の歴史、そして最近では色んな町工場の機械の動いている様子を集めた写真集も発見した。これらは道具のコレクションの写真といっていいだろう。 道具は面白い。色んな道具がある。日常生活の道具、工場生産の道具、農作業の道具、職人の道具、趣味の道具、音楽の道具、写真の道具、武術の道具、登山の道具、スポーツの道具、茶道の道具、「煙草道」の道具、勉強の道具、研究室の道具、医師の道具 −− 人の数だけ道具がある。人の営みにはすべて道具が介在する。 「ホモ・ファーベル」=「作る人」という言葉があるが、このような人と道具を切り離すことはできないだろう。人はみな自分の道具のコレクションを持ち、そのコレクションを愛し、自分の分身のように思っていることだろう。 そんな道具のコレクションを見るのは興味が尽きない。また、それを人が使いこなすのを見るのもまた驚きである。道具を見ると色々な人がどんな風に生活しているか、いかにその生活を大切にしているか、その人がどんな人であるか分かるような気がする。 田舎を歩いたときよく農家の作業小屋にぶつかった。そこにはたいてい壁一面にさまざまな農具がきちんと並べて掛けられていた。今では機械を使って簡単にすますのだろうが、かつてはすべて手作業や役畜の力を借りて農作業をしたのだろう。その道具が殆ど不要になってもなおきれいに飾られていた。 よく行くバイク屋も、雑然とした作業場の一隅にはあらゆる工具が、しかも最高級のものがきれいに整理されて置いてある、というより飾られている。われわれ素人には使い道がわからないようなものも多い。 これらはそれを使って働く人たちの自信と誇りを強く感じさせる。  私の趣味は写真の他に、音楽、登山、そして煙草くらいのものだが、それでもこれらのために道具を揃える。何年に一度も使わないのに道具を揃えたりすることもある。揃えた道具を眺めたり触ったりするのが、これがまた楽しい。趣味が先か、道具が先か、いったいどちらなのかはっきりしない一面もある。 私の趣味は写真の他に、音楽、登山、そして煙草くらいのものだが、それでもこれらのために道具を揃える。何年に一度も使わないのに道具を揃えたりすることもある。揃えた道具を眺めたり触ったりするのが、これがまた楽しい。趣味が先か、道具が先か、いったいどちらなのかはっきりしない一面もある。私の道具コレクションの中で特別なものは、父親の使っていた金槌、鋸、物差、という小さなコレクションである。みな古ぼけており汗がしみこみ、色あせている。いまや使われることはなく、親不孝の記念物としてただ置いてある。 仕事のための自分ならではの職人の道具も一式そろってはいるのだが、そろっているのは頭の中だけで実際にはあちこちに雑然と散らばっており、残念ながらいま他人様にお見せできる状態ではない。 風景写真は消滅するか
「風景とは景色である。風景画とは自然の景色を描いた絵画である」−−国語辞書にはそう書いてある。つまり風景写真とは自然の景色を写した写真である。 そのような写真を撮れる場所は大部分日本から消滅したかに思える。ごくごく小さな範囲を除いては。カメラをどこに向けても不自然な人工の構築物が入ってくる。 私は丹沢の麓に住んでいるのだが、もう何年もの間その山に写真を撮りに行っていない。どうしても行く気になれない。 10年前はまだよかった。丹沢はそう呼ばれているとおり「山塊」だった。山の裏には秘境ともいうべきひなびた村があった。ところがその村はダムになり、村ではなく観光の町になろうと勢いこんでいる。もはや丹沢は山の頂上あたりにしか残っていない。林はその半分が杉の植林である。あらゆる川には堰堤が作られ,あらゆる谷には砂防ダムというものが山頂めざしてはい登っている。通行量の全くない広い道が山中を縦横に走っている。 どこも同じような状態だろう。少なくとも私が見てきた限りではそうだ。 日本で風景写真を撮ることはもはや絶望的な状態ではないか、風景写真はいま消滅しようとしているのではないか・・・そんな風にも思えてくる。 その根は深い。これらはみな「際限なく自然を開発する」という人間社会の本能的ともいえる活動の結果だからだ。その底には、自然は人間に対立するものであり、人間の活動の対象に過ぎず、人間の要求に応じていつでも「開発」を待っている、という西洋伝来の伝統的な信念がある。 しかし、自然は人間を超えたものであり、われわれに限りない感動と洞察を与えてくれるものだ。自然は畏怖すべきものであり、そこから無限の意味を感じ取るべきものだ。だからこそ「風景写真」があり得る−−私はそう考えている。 こんな状況の中で、それでも何とかして自然の風景写真が撮れないだろうか? とりあえず一つの代案は、人工を含めた自然を受け入れることである。この人工は古くから自然の中に生きてきた人間の営みのなごりでなければならない。写真の中に人や家があってもよいだろう。風景にとけ込んでいるならば。 もう一つは、風景となり得る人工を探すことである。古い町並み、農村のたたずまいなどはその資格があるかも知れない。古い時代は自然との調和に生きていた。自然と人工の産物がともに違和感なく受け入れられる。 また長時間露光で撮った人一人いない都会もよいかも知れない。それは都会の終わりを暗示するからだ。 そして、廃墟がある。それは自然に復帰しつつある人工である。 一つ、救いがある。それは日本の人口がこれから減少してゆくことである(参照)。あと数十年で何割か減るそうだ。また経済の高度成長はもはやないと言われている。 人間活動の自然への圧力は弱まるだろう。かつての過剰な人工物は崩壊し廃墟となるだろう。自然が再び取り戻されるに違いない。 廃虚が流行だとか
いつの頃からか、どういうわけか廃虚に心を引かれていた。 多くの廃虚がある・・・インカ、アンコールワットから町の中でくちて行く家々まで。そして故郷の我が家もだれも住まない廃虚となって、年々草木にうずもれて行きつつある。 どういうわけかそれらを見てなんとなく安堵感をおぼえる。なぜだろう? 廃虚の写真を私がはじめて目にしたのは92年ころだった。アサカメで「ニューフォトの旗手たち」としてあべ美鈴という女流写真家が2枚のヨーロッパ風住居の廃虚のモノクロ写真とともに紹介された。その印象は強烈だった。廃虚に惹かれる自分をはっきりと意識したのはこの時が初めてだった。数年、それは心の中に沈潜していた・・・そして今年初め何度か新聞の記事が再び廃虚を思い出させた。 それによると、最近「廃虚」が若い人の間に静かな人気を呼んでいるというのだった。写真集もいくつも出ているという。 たとえば「懐古文化綜合誌萬」、「鉄道廃線跡を歩く」、「廃線跡の旅」、「棄景シリーズ」、「廃虚遊戯」、「廃虚巡礼」、「JAPAN UNDERGROUND」、「TOKYO NOBODY」、「小屋の肖像」などなど。 新聞の解説によれば、うちすてられて行くものに対して「わび、さび」を見ている、汚さがむしろ新鮮に見えている、朽ちて行く美、崩壊寸前の遺跡に生成の力・・・・などなど、いろいろな見方、受け取り方があるようだ。「実在感や熱っぽさが希薄になっている時代感覚」とかいている記事もある。 私の感じ方からすれば、「廃虚」は一つの予感である。かつて古代の文明がみな砂漠や密林におおわれてしまったように、きっと我々の眼前の文明も・・・という予感である。写真は被写体であるとともに自分の心の奥底の反映である。この予感がひそかにだんだん広まって行きつつあるのではないか。 そしてそれを密かに待ち望んでいる一部の自分があることに気がついた。なんということか !
また最近(5月22日)の新聞によると、カンヌの映画祭に出品された日本のいくつかの映画は「世界で一番終末感をただよわせている」と評されたそうだ。写真も映画も同じ流れにあるのかも知れない。
・・・終末への期待、破滅の予感・・・それは本当にこの世の中に潜在する潮流なのだろうか? そして、今日(6月22日)の日経新聞を見て驚いた。 「寂寥の景色」と題するコラムに、ジョルジオ・キリコが、そしてかれが「形而上絵画」を発見した最初のものだとされる「予言者の報酬」という作品が紹介されていた。この絵はデルヴォー、ダリを思い起こさせる。これらでは偉大な文明の「廃虚」であるギリシャや、砂漠、つまり自然の廃虚が舞台である。そして「永遠」がある。 また今日(8月11日)の日経新聞のコラムによれば、ダビンチが描いた大作の殆どでは背景がこの世にない異星のような荒涼とした景色で、「廃墟となった橋」までも描かれており、世界が滅んだ後を思わせるものだそうである。 かれらは偉大な預言者たちだったのだろうか? われわれもその見通した時間の流れの中にあるのだろうか? |